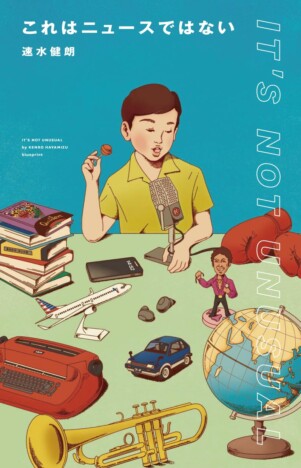現在放送中のフジテレビ系木曜劇場『グッド・ドクター』の主題歌として注目を集め、8月2日に先行配信された「Hikari」が、8月29日にCDでリリースされる。これまでのandropの曲でも多くテーマとして描かれてきた“Hikari=光”をタイトルにしたこの曲は、優しく、温かなタッチの曲だが、一方でとてもピュアな力強さを持つ。〈光に変えてゆくよ どんな暗闇も〉、〈絶望の底に飲み込まれそうなら いつだってあなたを連れてゆく〉。そう言って、グッと手を掴んでくれるこの曲は、andropの曲の中でも眼差しの深さがあって、より能動的でもある。
これまでも多くのドラマや映画主題歌を手がけてきたandropだが、内澤崇仁(Vo/G)によれば、今回の曲はより多くの時間を費やし、ドラマのスタッフとも納得のいくまでやりとりを重ねたという。ドラマという作品への寄り添い方も、一歩踏み込んで、ともにひとつの作品を作り上げていくような感覚だったのだろう。ドラマの中でこの「Hikari」が流れるとき、この歌は時に喜び、励まし、また一緒に涙を流すようないちキャストとなり、あるいは狂言回し的な役割を担っている。ごく自然に、ストーリーの一部となっている。この「Hikari」という曲に、どのように取り組み、完成をしたのか。それはandropにとって、どんな曲となったのか、フロントマン・内澤に話を聞いた。(吉羽さおり)
「ドラマを初めて見る人にも、伝わるようなものを作りたい」
ーーニューシングル「Hikari」は、いろんな人が心寄せられるとてもいい曲だなと思いました。今回は、ドラマ『グッド・ドクター』の主題歌でもありますが、どんなふうにスタートしていった曲でしたか。
内澤崇仁(以下、内澤):はじめに、『グッド・ドクター』という韓国ドラマの日本版を制作するということで、その主題歌をお願いできないかというお話をいただいて。それが4月に入る前で、5thアルバム『cocoon』のリリースあたりだったと思いますね。
ーーそのときは、こういう内容にしてほしいとか、ドラマ制作側からのオーダーはあったのですか。
内澤:5月にドラマ制作サイドと打ち合わせをする機会があったんです。その間までには特に、「どういうもので」というオーダーはなかったので、なんとなく打ち合わせ前までに曲を作っておこうかなと思って。でもその時点で、まだ日本版の脚本やキャスティングもちゃんと決まっていないくらいのところだったので。まずはオリジナルの、韓国ドラマをじっくりと観て、これが日本版だったらどういうものになるんだろうなと想像しながら、打ち合わせ前までに4曲くらい作ったんです。それを打ち合わせの時に持っていったという感じでしたね。で、そのはじめの打ち合わせの時に、医療ドラマで、人間の生死を扱うヒューマンドラマにしたいという話を聞いて。
ーーなぜその主題歌をandropにお願いしたか、という話も打ち合わせでは出たんですか。
内澤:オーダーとしては、andropはデジタルな雰囲気も持っているんですけど、今回はピアノをメインにして作ってもらいたいと。曲のイメージとしては、人間味が伝わるような生の雰囲気のものがあるという話はありましたね。
ーー最初の打ち合わせ時に作っていった4曲は、どんな感じだったんですか。
内澤:いろんなパターンを考えていきました。韓国版のドラマでは、前半は人間関係を描いていて、中盤を過ぎたあたりからは恋愛の話も増えていって。それぞれの話のエンディングも、つらい終わり方もあれば、あったかい感じで終わるパターンもあったので。そのいろんなシチュエーションでかかってもおかしくない曲がいいだろうなと思って、4曲作っていったんです。速いものもあれば、スローなバラードも用意して持っていきました。
ーー今回の「Hikari」はそのうちのひとつだったのですか。
内澤:これはまた、違うものですね。打ち合わせの時に持っていった4曲を聴いてもらったんですけど、「すごくいい曲だと思うんだけど、イメージしているドラマとはあまり仲良くなれないかな」という話があって。それで、ピアノがメインの曲を、2パターン作ってほしいと言われたんです。毎回、患者や出演者の心の闇を溶かしていくような終わり方のドラマになっていくと思うから、そういう時に流れる楽曲であってほしいということで、ミディアムテンポなバラードがひとつ。話によっては悲しい場面で終わることもあると思うから、そのミディアムなバラードをアレンジしたスローな曲、その両面を兼ね備えている楽曲を作ってほしいというのがありましたね。
ーー難しいオーダーですね。これまでもドラマ主題歌など手がけてきましたが、今のようなオーダーっていうのはあったんですか。
内澤:2つを兼ね備えたというようなものはなかったですね。デジタルっぽいものとか、既存曲を例に「こういう雰囲気のものが合いそうですね」という、具体的なイメージをもらうことはありましたけど。
ーーそこから、この「Hikari」という曲を生み出していくのは、どう向き合っていったんですか。
内澤:それまでの4曲は、イメージで曲を作っていたんですよね。オリジナルのドラマを観て、こういう曲が合うだろうなとか。主人公が自閉症・サヴァン症候群で、小児病棟が舞台ということで、自閉症に関しての本を読んだり、小児外科医が書いた本を読んで、得た知識から想像して歌詞を書いていたんです。でも、それだけだと多分ダメだろうなと、その打ち合わせをした時に思ったんです。映像や見聞きしたものでなく、実際に経験をしたリアルなものが何パーセントかでも入っていないと、このドラマに沿う曲はできないだろうな、と。それで、もし可能であれば病院に行かせてもらいたいという話をしたんです。そうしたらちょうど、何日か後に、ドラマ制作側が病院に取材に行くということだったので、そこに同行させてもらったんです。
ーー実際に取材にまで。
内澤:4月の後半から『cocoon』のツアーが始まっていたんですけど、福岡のライブの翌日に、病院に取材に行けるということだったので。朝、福岡から移動して、病院の取材に行きました。
ーー実際に、病院に足を運んでみて、どうでしたか。
内澤:僕が伺わせてもらったのは、埼玉県立小児医療センターという、さいたま新都心にある病院なんですけど。ここ数年でさいたま新都心に移転した病院で、日本でも有数の最新医療機器が揃っていて、手術室もたくさんある場所なんです。先生に手術室やICU、病室とかを案内してもらって。実際に、ICUを見るのも初めてだったし、本当に、つらくなりました。まだ名前もない生まれたばかりの、全身に管を通されている赤ちゃんが何人もいるんです。脳に水が溜まって膨らんでしまった子や、多分生後ある程度時間が経っているのに、まだ名前がない子もいて。なぜかと聞いたら、病気でまだ性別がわからないという……。病気の赤ちゃんがこんなにもいるんだっていう現状にまず、衝撃を受けたのと。あとは、小学生くらいになっても、動けずにいる子だったり。片手には車のおもちゃを持っているけど、ベッドの上に横になっていたりとか。近くには小学校があるけれど、小学校にいけない子もいるんですよね。そういうのを見ていると、改めて現実っていうのはすごくつらいものなんだなって思って。
ーー言葉にならないですね、実際に目の前にしてしまうと。
内澤:ドラマのプロデューサーも一緒にいたんですけど、「こうしたお子さんを持つ親御さんも、ドラマを観るかもしれないし、僕らはこういう小児医療の現状も知ってもらいたい思いもある」という話をしていたんです。だったらなおさら、そうした人にも届く楽曲にしないといけないなというのはありました。あとは、ドラマを初めて見る人にも、心にくるもの、伝わるようなものを作りたいなって、その時に改めて思いましたね。
ーー実際にいろんなことを知って、体験したからこそ、書くのが難しくなってしまうということもありそうですが。
内澤:自分が携わるにあたって、どんなことが言えるんだろうということは、ずっと考えていました。
ーー取材の前に伺っていたんですが、今回はギリギリまで何度も何度も書き直していたそうですね。
内澤:7月12日にドラマの第1話がオンエアだったんですけど、6月10日までに完パケする予定で動いていたんです。でも、ドラマの第1話がはじまる直前まで1コーラスすらできていなくて。7月9日の朝に、テレビサイズのものが完成して(笑)。どうにか、第1話で曲が流すことができたんですけど。
ーーそうだったんですか!?
内澤:第1話が流れている頃も、僕はまだフルの歌詞を考えていました。結構な難産というか。最後まで歌詞を書き直していました。その前までは、曲を何パターンか作ったり、イントロが決まって、Aメロが決まって、サビが決まって、でもサビとAメロを埋めるBメロが決まらないとか、そういうのでずっとやり取りをしていて。ドラマがはじまっても、まだ最後まで曲ができあがっていなかったというのは、あまり僕も体験したことがないし、聞いたことない話だったので。
ーーたしかにそうですね。
内澤:でもそこまでやらせてもらえるっていうのも、お互いに熱量がないとできないことだと思うんです。向こうもリスクを背負ってしまっていますしね。そういった、熱量のある現場だと思いますね、この『グッド・ドクター』の制作チームは。とにかく妥協しないっていう……途中、本当に自分は才能がないんじゃないかなって思った瞬間もあったんですけども。ここで諦めるわけにはいかないって思いながら、ずっとやっていましたね。ツアーが始まってしまってもいたんですけど。
ーーそのツアーのテンションとも、また全然違うからこそ大変ですね。
内澤:ツアー中も、ホテルでずっと歌詞を書いて。ライブ終わって、ちょっと打ち上げをしたらまた朝まで歌詞を書いて、というのを、ずっと続けていました。