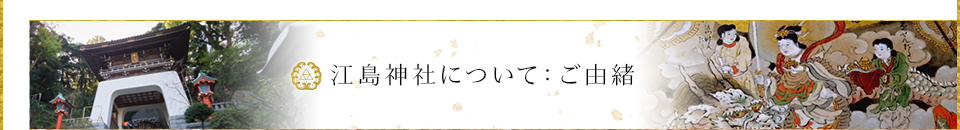江の島のはじまり
江の島湧出については諸説ありますが、『江島縁起』では、欽明天皇十三年(552年)四月十二日の夜から二十三日の朝まで大地が震動し、天女が十五童子を従えて現れ、江の島を造ったと表現しています。このことを社伝では、「欽明天皇の御宇 神宣
により詔して 宮を島南の竜穴に建てられ 一歳二度の祭祀この時に始まる」と記しており、欽明天皇の勅命で、島の洞窟(御窟・現在の岩屋)に神様を祀ったのが、江島神社のはじまりであると伝えています。欽明天皇は、聖徳太子よりも少し前の時代の天皇で、この頃、日本では仏教が公伝され、日本固有の神道と外来の仏教が共に大事にされていました。
名僧たちがご神徳を仰ぎに訪れた島
その後、文武天皇四年(700年)に、役小角という修験者が、江の島の御窟に参籠して神感を受け、修験の霊場を開きました。これに続き、泰澄、道智、弘法、安然、日蓮
などの名僧が、御窟で次々に行を練り、高いご神徳を仰いだと伝えられています。そして、弘仁五年(814年)に空海が岩屋本宮を、仁寿三年(853年)に慈覚大師が上之宮(中津宮)を創建。時を経て、建永元年(1206年)に慈覚上人良真が源實朝に願って下之宮(辺津宮)を創建しました。
※奥津宮は、岩屋本宮に海水が入りこんでしまう四月~十月までの期間、岩屋本宮のご本尊が遷座されたところで、江戸時代までは本宮御旅所(ほんぐうおたびしょ)と言われていました。創建年代は不詳ですが、風土記などの資料から1600年代の創建と考えられています。
“戦いの神”から“芸能・音楽・知恵の神”へ
鎌倉時代には、岩屋に参籠して戦勝祈願を行った源頼朝が八臂弁財天と鳥居を奉納。また後宇多天皇
は、蒙古軍を撃ち退けた御礼として、江島大明神の勅額を奉納されました。このことから“戦いの神”としての弁財天信仰が広がり、東国武士たちが多く江の島を訪れるようになりました。江戸時代になってからは泰平の世となり、江島神社は“戦いの神”から“芸能・音楽・知恵の神”として、また“福徳財宝の神”として信仰されるようになりました。慶長五年(1600年)には徳川家康も参詣、代々の将軍たちも、病気の治癒、安産、旅行の安全などを祈願したと伝えられています。
時代を経ても変わらないご神威
それから後、慶安二年(1649年)に仏教との習合により、江島神社は金亀山与願寺
と号しますが、江島大神としてのご神威はいささか曇り給うことなく、ご神徳はいよいよ広大に仰がれました。明治初年の神仏分離によって、仏式を全廃して純神道に復し、改めて「江島神社」と号し、これまでの本宮と御旅所は奥津宮、上之宮は中津宮、下之宮は辺津宮と改称し、海の神、水の神、幸福・財宝を招き、芸道上達の功徳を持つ神として仰がれています。