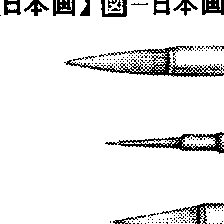古く中国から伝えられ,長い歴史の中で形成された絵画。膠(にかわ)を接着材として天然産の色料(近代以降,人造色料も現れた)や墨を用いて表現される。明治以後,西洋伝来の油絵具を使う油絵(洋画)と区別して,これに対して用いられた言葉である。しかし現在,日本画は大きく変わりつつあり,新しい表現技術の採用などによって洋画との区別はつけにくくなってきている。にもかかわらず,日展でも日本画と洋画は科を異にしているし,院展(日本美術院展覧会)のように日本画だけの展覧会もあり,社会通念としてははっきりと区別されている。それゆえ日本画と洋画を分けて説明するには,〈材料〉と〈技法〉を中心に考えてみるのがよい。日本画の歴史と状況については,〈明治・大正時代美術〉および〈日本美術〉の項目を参照されたい。
材料
基底材料
日本では絵は古代からさまざまな素材の上に描かれてきた。和紙や絹に描かれたもののほかに,古墳の石室や法隆寺金堂など寺院の板壁,皮革などに描かれたものが残されている。このように日本画は膠による絵具の定着さえ可能ならば,さまざまな材料に描くことができる点が特色といえる。しかし,なかでも絹と紙とに描かれたものが数量的にも多い。現在多く使われている和紙はコウゾ(楮),ガンピ(雁皮),ミツマタ(三椏),麻などを漉(す)いた,雁皮紙,麻紙,鳥の子紙などである(和紙)。絹は東洋の絵画の長い歴史の中で主流をなした素材で,その美しい光沢が絵具の色を引きだしている。絵画用の絹は衣服に使用されているものと基本的には変わらないが,含有成分セリシンを取り除いていない生絹を織ったものである。
念紙
墨や絵具は描き直しがしにくいため,描く前に十分構想を練り,下図を作るのが普通である。念紙は下図を本画用の基底材料に写すための紙である。薄く丈夫な和紙に松煙を酒などで溶いてよくしみ込ませたもので,下図の下に置き,上から骨筆でなぞって基底物に写す。その後,墨などでさらに絵描きし,残った松煙などを羽ぼうきではらう。ほかに,朱土や,胡粉(ごふん)を塗ったのも使われる。
絵具
日本画の絵具を大別すると,古代より使われていた天然に産出する鉱物を砕いた岩絵具と,動植物から抽出した色素を顔料とする絵具,そして近代以降開発された人造の絵具とに分かれる。ここでは天然色料を中心に述べる。
青色には群青(ぐんじよう),白群などの岩絵具と藍(あい)が用いられる。赤色には辰砂(硫化水銀),朱(硫黄と水銀を混合し加熱して得るもので,赤口朱,黄口朱,鎌倉朱,古代朱,鶏冠朱,黒朱などの種類がある),朱土(酸化鉄),臙脂(えんじ)(動物性),明るいオレンジ色をうる丹(四酸化三鉛)が用いられる。緑色は緑青,白緑の岩絵具と籐黄と藍の混合,草の汁などから得る。黄色には黄土,籐黄,石黄(雌黄)が使われ,白色にはおもに胡粉(蛤粉),また白土,鉛白などの岩絵具が使われる。その他,雲母(きら)などが用いられる。以上に墨を加えたものが日本画の絵具の主要なものである。色数は少ないが,混色や重ね色で数を増し,また天然岩絵具は焼いて色に変化を与えることもある。これら天然絵具のほかに,現在では日本画の絵具の大半を占める新岩絵具がある。これは高温で溶解したときガラス質になるフリットに,高温で発色する金属酸化物を加えて坩堝(るつぼ)などで混合し,それを砕いて粒子別に分けたものである。ほかに合成絵具,棒絵具,泥絵具,顔彩などがある。
→絵具
箔,泥,砂子
箔(はく)には金,銀をはじめとし,プラチナなどが用いられる。金箔には厚さの違いと,銀や銅との合金による色の差があり,純金箔,山吹,青金(あおきん),水金などと呼ばれる。これを画面に貼ったり,散らして文様を表現することは古くから行われた。その方法は,まず竹のバレンにツバキ油などをつけ,それを箔合紙(箔と箔の間にはさんである)にのばし,この紙を箔に軽く接着させる。この作業を箔を〈あかす〉という。このようにして扱いやすくなった箔を,数度膠液を塗った紙,絹の画面上に,どうさ(礬水)液などで貼ってゆく。
古代から仏画などにみられる切(截)金(きりかね)は,仏師箔とよばれる銀を多く含んだ厚い箔と金箔を炭火で焼き合わせた後,軟らかな鹿皮の上にのせ,竹刀で細く切り,2本の筆を使って文様を描いてゆく技術である。砂子(すなご)は粗密各種類の網を張った竹筒に切廻し箔を入れ粒状にした後,再び竹筒に入れ棒などで竹筒をたたいて画面に落としてゆく技法で,装飾効果を高めるためのものである。泥(でい)は箔をつくる際に出る切廻し箔などを練り合わせたもので,金泥は膠で練り,火の上で焼きつけては溶きかえすという作業をくり返しながら使うと美しい発色が得られる。また金泥を塗った後,貝殻や動物の牙などで上面をこすり,輝きを増したりもする。銀箔は空気に触れると酸化し黒変色するので,上からどうさ液を塗って保護する。
墨
〈墨に五彩あり〉といわれるように,日本画において墨の果たす役割は水墨画に限らず重要である。松煙製の墨は青墨とも呼ばれ青味をおび,絵画では好んで使われる。またどんな絵具にも溶けやすい性質を利用して,胡粉に混ぜた貝墨(かいずみ)などを各色に混入し,日本画の表現を広げている。また良墨の粒子をきれいに水分に分散させ,発色効果を引きだす用具として硯(すずり)も重要である。
膠日本画を支える大切な接着材であり,古くから使われてきた。一貫目(3.75kg)で3000本ぐらいになるため三千本膠と呼ばれるものや鹿膠,粒膠,鬼膠などがある。まず水に浸して十分膨潤した後,湯煎などによって約70℃で溶かす。これを布で漉して使う。濃度は各作家によって異なるがおおよそ三千本膠5本に水200㏄ぐらいが標準である。
どうさ(礬水)
膠液にミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム)を溶かした混合液で,日本画を描く上でさまざまに使用される。一般には基底材料である和紙や絹の上に塗られる。これは基底物の吸湿性をおさえて膠と絵具を画面に定着させるためであるが,板絵などでは板に含まれる樹脂がにじみ出るのを防止する。その他,金銀箔の接着や銀箔・銀泥の表面に塗られるなどその用途は広い。しかし,どうさはミョウバンを含み,使用を誤るとかえって素材料の劣化を早めることもあるので,過度の使用はいましめるべきである。
筆,刷毛
筆は用途別にさまざまの種類があるが,もとは書も画も同一で,明治期に入りヨーロッパの多様な表現法の影響を受けて,種類を増してきた。毛には羊,鹿,馬,兎,イタチ,タヌキ,テン,猫,ネズミなどがあり,それぞれの特性を生かして使われている。付立(つけたて)筆,面相筆,線描き筆,彩色筆,隈取筆などがある。付立筆は線描きや没骨(もつこつ)技法などに用途が広く,墨絵に便利。面相筆と線描筆は細い線を引くために用いる。彩色筆は絵具,膠の含みがよいもの,隈取筆はぼかしや隈をとるのに使う。刷毛には幅1寸から8寸まで各種あり,一定幅に均一に塗る絵刷毛,広い面積をぼかしたりするカラ刷毛,どうさを塗るどうさ刷毛と,筆を横に何本もつなげた連筆に大別される。
印,印泥
絵を描き上げ,作家の名をしるし,印を押して日本画は完成である。印泥は朱をヒマシ油,松脂,白蠟などと練り合わせたもので,時間をかけて十分に練られたものがよい。印材は作家の名前や号を彫ったもので,石,木,竹や陶器で作られる。石材には田黄や鶏血石などさまざまな美しい石が用いられる。印矩は印を押すとき印材を固定する定規である。
技法
大きく単色画と彩色画に分けられる。単色画は多くは墨一色である(まれに朱一色,藍一色がある)が,この場合,下図に相当するデッサンは除いてタブローとしてのみいうと,線だけで表現するものを〈白描〉,墨を濃淡の面で表すものを〈水墨画〉という。白描は〈しらえ〉ともいい,日本でも古くからある技法で,清潔で,流動感を表すに好適である。正倉院宝物の《鳥毛立女屛風》や,鳥羽僧正覚猷筆と伝えられる《鳥獣戯画》などがその好例である。また輪郭線で物象の形を囲むのを鉤勒(こうろく)法といい,仏画などのように太い細いのない線でくくるのを鉄線描,反対に抑揚の多いのを肥瘦(ひそう)のある線などという。水墨画は墨で物体の面をとらえ,マッスをつくり,また空間の深み,奥行きを表す。そのために墨の濃淡を駆使するというものである。いずれにしても単色画は,直截・端的な表現法で,この簡素な直接法の表現は,東洋ことに日本的性情に適して発展し,線や墨に意味や価値を重く託して,色彩の扱いにまでその意味や方法を延長していったと思われる。今でも日本画の生命は線と墨にあるが,現代の日本画に完全に当てはまるというわけにはいかない。
洋画のような即物的で執拗な表現能力に欠け,簡素で素朴な,また暗示的な表現法が今も特徴であるが,墨と線だけではとうてい出しきれぬ感覚を今日では経験している。今日の日本画は,彩色画が圧倒的である。彩色画にはつぎの種類がある。(1)平安時代後期に〈濃絵(だみえ)〉と称し,後世〈極彩色〉と称した濃彩画。(2)絵巻物などにみる〈線〉を没却しない程度の濃度または線と並行する濃淡や動きのある彩色法。(3)室町時代以後,あくまで墨を主にして,藍や緑の透明な水絵具,あるいは胡粉や朱や代赭(たいしや)を用いても,墨の意味を補足する〈淡彩画〉。(4)輪郭線なしに物象を表す〈没骨法〉(これは墨の場合にもいう)。(5)同じく輪郭線なしだが,色で物象の生態を即写的に描写する〈付立法〉。(6)紙の吸湿性を利用する〈ふくさがき〉。(7)反対に絵具を紙面にしみ込ませず,たまった絵具の層が溶け合った偶然の効果を待つ〈たらしこみ〉。(8)金・銀箔を画面に置く〈箔押〉。(9)それを細かくして蒔(ま)く〈砂子〉。以上のようにいろいろあるが,しだいに厚塗りとなり,マチエールの迫力にたよるようになってきて,従来とちがった表現様相を呈するようになってきた。
執筆者:林 功