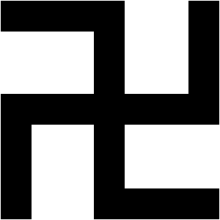「寺」という漢字は、本来、中国漢代においては、外国の使節を接待するための役所であったが[2]、後漢の明帝の時にインドから訪れた2人の僧侶を鴻臚寺に泊まらせ、その後、この僧侶達のために白馬寺を建てさせ、住まわせたことが、中国仏教寺院の始まりである[2]。
寺院の建造物は、礼拝(らいはい)の対象を祀る「堂塔」と、僧衆が居住する「僧坊」とに区分される。
「堂塔」は、釈迦もしくは仏陀の墓を指すものであって、祖形は土饅頭型であったが、暑さを避けるために傘を差し掛けたものが定着して、中国などで堂塔となった。日本にも中国様式が入ってきて、三重塔・五重塔・七重塔などが立てられ、土饅頭の痕跡を残した多宝塔などが出現する。日本庭園に十一重や十三重の石塔などの多層塔を建てているが、これも同意のものである。
「僧坊」は、インドではヴィハーラと名づけられて、僧侶が宿泊する場所であり、祇園精舎(ぎおんしょうじゃ、jetavana-vihāra)のように釈迦在世の時代から寄進された土地を指したが、次第に僧坊が建設されたり、石窟に住んだりした。中国に入ると僧坊が建設されることが多くなり、堂塔が併設されたので、寺院というと、堂塔と僧坊が同所にあることが普通となる。
最初期の出家者の一時的定住地はāvāsa(住処)またはārāma(園、おん)と呼ばれた。都市郊外の土地が僧伽に寄進されたものを僧伽藍摩(そうぎゃらんま、saṃghārāma)・僧伽藍、略して伽藍(がらん)といわれた。出家者の定住化に伴って僧院が形成された。精舎(しょうじゃ、vihāra)・平覆屋・殿楼・楼房・窟院の5種がある。精舎や窟院では広間と房室を中心として諸施設が整備された。
信仰の対象としての「仏塔」は、はじめ在家信者によって護持されたが、起塔供養の流行に伴って僧院中に建設され、塔を礼拝の対象とする支提堂(しだいどう、祠堂のこと)と支提窟が造られた。やがて塔の崇拝は仏像の崇拝に代わり、中国・日本の金堂(こんどう)の原型となった。
「寺(じ)」は、「役所・官舎」の意(前述書)。西域僧が中国に仏教を伝えた時、はじめ鴻臚寺(こうろじ)に滞在し、のちに白馬寺(はくばじ)を建てて住まわせた。以後、宿泊所に因んで僧の住処を「寺」と呼ぶようになった。「院」は、寺中の別舎を指している。
日本語の「寺」の訓読みである「てら」というのは、パーリ語のthera(長老)の音写であるともいわれるが明らかではない[3]。
中国や日本の寺院では、寺院の名称に山号を加えることがある(「比叡山延暦寺」など)。詳しくは記事「山号」を参照のこと。
仏教以外の宗教の寺院
編集
- ^ 古刹、名刹のように「刹」(さつ)が使われることもある。