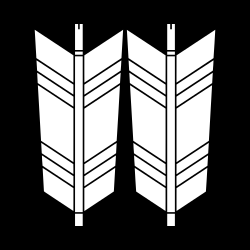この項目 こうもく 武具 ぶぐ 狩猟 しゅりょう 具 ぐ 説明 せつめい
矢 や 武具 ぶぐ 狩猟 しゅりょう 具 ぐ 一種 いっしゅ 木 き 竹 たけ 金属 きんぞく 作 つく 棒 ぼう 端 はし 軌道 きどう 安定 あんてい 羽根 はね 取 と 付 つ 反対 はんたい 側 がわ 端 はし 用途 ようと 応 おう 物 もの 取 と 付 つ 主 おも 弓 ゆみ 弾力 だんりょく 利用 りよう 発射 はっしゃ 投擲 とうてき 物 もの 投 な 矢 や 呼気 こき 空気 くうき 利用 りよう 物 もの 吹 ふ 矢 や 箭 や 字 じ 用 もち
矢 や 一手 いって 和 かず 弓 ゆみ 用 もち 矢 や 現在 げんざい 矢 や 竹 ちく 端 はし 反対 はんたい 端 はし 矢 や 羽 わ 筈 はず 作 つく
矢 や 長 なが 自分 じぶん 矢束 やつか 首 くび 中心 ちゅうしん 横 よこ 伸 の 腕 うで 指先 ゆびさき 手 て 指数 しすう 本分 ほんぶん 長 なが 安全 あんぜん 上 じょう 好 この 平家 ひらか 物語 ものがたり 十 じゅう 二 に 束 たば 三 さん 伏 ふく 拳 こぶし 幅 はば 個 こ 分 ぶん 加 くわ 指 ゆび 本 ほん 分 ぶん 幅 はば 表記 ひょうき
矢 や 作 つく 職人 しょくにん 矢 や 師 し ゆがけ を作 つく 職人 しょくにん 師 し 弓 ゆみ 弓 ゆみ 師 し 弓矢 ゆみや 鉄砲 てっぽう 比 くら 科学 かがく 技術 ぎじゅつ 的 てき 原始 げんし 的 てき 消耗 しょうもう 品 ひん 矢 や 含 ふく 全 すべ 製造 せいぞう 職人 しょくにん 技 わざ 頼 たよ 点 てん 弾 たま 火薬 かやく 製造 せいぞう 知識 ちしき 誰 だれ 労働 ろうどう 集約 しゅうやく 型 がた 産業 さんぎょう 銃器 じゅうき 普及 ふきゅう 推進 すいしん 一因 いちいん
現代 げんだい 弓道 きゅうどう 用 もち 上 うえ 鉄製 てつせい 打 だ 根 ね 真鍮 しんちゅう 製 せい 打 だ 根 ね 巻藁 まきわら 矢 や 丸根 まるね 縄文 じょうもん 時代 じだい 黒曜石 こくようせき 等 ひとし 石鏃 せきぞく 鮫 さめ 歯 は 動物 どうぶつ 骨 ほね 角 かく 作 つく 弥生 やよい 後期 こうき 急速 きゅうそく 鉄製 てつせい 鉄 てつ 替 か 鏃 (英語 えいご 版 ばん 参照 さんしょう 使用 しよう 目的 もくてき 様々 さまざま 形 かたち 発達 はったつ 現在 げんざい 鉄 てつ 製 せい 用 もち 稀 まれ 真鍮 しんちゅう 製 せい 用 もち 人 ひと 箆 へら 挿 さ 込 こ 被 かぶ 二 に 種類 しゅるい 使用 しよう
長 なが 使用 しよう 磨 す 減 へ 交換 こうかん
矢 や 持 も 日置 ひおき 流 りゅう 持 も
流派 りゅうは 板付 いたづけ 矢 や 根 ね 単 たん 根 ね 呼 よ
戦闘 せんとう 一般 いっぱん 的 てき 小 ちい 軽 かる 物 もの 遠距離 えんきょり 用 よう 逆 ぎゃく 大 おお 重 おも 物 もの 近距離 きんきょり 用 よう 刃 は 部分 ぶぶん 広 ひろ 大 おお 鎧 よろい 付 つ 敵 てき 対 たい 細身 ほそみ 返 かえ 様 よう 鎧 よろい 特 とく 鎖帷子 くさりかたびら 敵 てき 対 たい 刃 は 太 ふと 重 おも 板金 ばんきん 鎧 よろい 着 き 相手 あいて 対 たい 使用 しよう 火矢 ひや 用 よう 燃 も 布 ぬの 絡 から 素材 そざい 丈夫 じょうぶ 鉄 てつ 緑 みどり 錆 さび 銅 どう 着弾 ちゃくだん 砕 くだ 散 ち 石 いし 使 つか
木製 もくせい 木 き 捕 と 具 ぐ 矢 や 項 こう 参照 さんしょう
矢 や 棒 ぼう 部分 ぶぶん 竹 たけ 矢 や 竹 ちく 呼 よ 作 つく 矢柄 やがら 矢 や 箆 へら 竹 ちく 矢 や 竹 ちく 呼 よ 現代 げんだい ジュラルミン や炭素 たんそ 繊維 せんい 強化 きょうか 製 せい 学生 がくせい 中心 ちゅうしん 用 もち アーチェリー に倣 なら シャフト と呼 よ
箆 へら 形 かたち 以下 いか 三種 さんしゅ
一文字 ひともじ 文字通 もじどお 端 はし 端 はし 太 ふと 変 か 現在 げんざい 主流 しゅりゅう 杉 すぎ 成 しげる 径 みち 杉 すぎ 木 き 根 ね 矢尻 やじり 部 ぶ 徐々 じょじょ 細 ほそ 様子 ようす 名 な 付 つ 竹 たけ 生育 せいいく 適 かな 工作 こうさく 少 すく 丈夫 じょうぶ 麦 むぎ 粒 つぶ 中央 ちゅうおう 最 もっと 太 ふと 両 りょう 端 はし 細 ほそ 空気 くうき 抵抗 ていこう 受 う 際 さい 振動 しんどう 率 りつ 遠 とお 威力 いりょく 弱 よわ 飛 と 遠矢 とおや 鏑矢 かぶらや 用 もち 一 いち 組 くみ 矢 や 節 ふし 位置 いち 一本 いっぽん 矢 や 節 ふし 四 よっ
射 い 付 づけ 節 ぶし 鏃 から5cm位 い 節 ふし 矢 や 持 も 小笠原 おがさわら 流 りゅう 持 も 箆 へら 中 ちゅう 節 ぶし 矢 や 中央 ちゅうおう 節 ふし 袖 そで 摺 すり 節 ぶし 矢 や 中央 ちゅうおう 筈 はず 側 がわ 節 ふし 着物 きもの 着 き 矢 や 番 つが 袖 そで 摺 す 呼 よ 押取節 ぶし (おっとりぶし)ともいう。羽中 はなか 節 ぶし 矢 や 羽 わ 中 なか 節 ふし 甲 きのえ 矢 や 乙矢 おとや 矢 や 羽 わ 鷲 わし 下 した 甲 かぶと 矢 や 上 うえ 乙矢 おとや 矢 や 取 と 付 つ 羽 はね 単 たん 羽 はね 呼 よ 鷲 わし 鷹 たか 白鳥 しらとり 七面鳥 しちめんちょう 鶏 にわとり 鴨 かも 様々 さまざま 種類 しゅるい 鳥 とり 羽 はね 使用 しよう 特 とく 鷲 わし 鷹 たか 猛禽 もうきん 類 るい 羽 はね 最 さい 上品 じょうひん 中 ちゅう 近世 きんせい 武士 ぶし 間 あいだ 贈答 ぞうとう 品 ひん 使用 しよう 部位 ぶい 手羽 てば 尾羽 おは 幅広 はばひろ 尾羽 おは 一番 いちばん 外側 そとがわ 部位 ぶい 石打 いしうち 最 もっと 丈夫 じょうぶ 希少 きしょう 価値 かち 高 たか 珍重 ちんちょう
鳥 とり 羽 はね 反 そ 向 む 表裏 ひょうり 半分 はんぶん 割 さ 使用 しよう 本 ほん 矢 や 使 つか 羽 はね 裏表 うらおもて 同 おな 向 む 揃 そろ 矢 や 種類 しゅるい 矢 や 前進 ぜんしん 後 うし 見 み 時計 とけい 回 まわ 回転 かいてん 甲 きのえ 矢 や 早 さ 矢 や 兄 あに 矢 や 書 か 逆 ぎゃく 乙矢 おとや 弟 おとうと 矢 や 書 か 甲 かぶと 矢 や 乙矢 おとや 合 あ 対 つい 一 いち 手 て 射 い 甲 かぶと 矢 や 射 い
矢 や 羽 わ 矧 はぎ 呼 よ 糸 いと 箆 へら 固定 こてい 矧 はぎ 本 ほん 矧 はぎ 筈 はず 側 がわ 矧 はぎ 末 すえ 矧 はぎ 矢 や 作 つく 矢 や 矧 は
矢 や 羽 わ 数 かず 種類 しゅるい 二 に 枚 まい 羽 わ 原始 げんし 的 てき 羽 はね 数 すう 軌道 きどう 安定 あんてい 儀式 ぎしき 用 よう 儀仗 ぎじょう 用 もち [ 1] 飛 と 軌道 きどう 安定 あんてい 性 せい 得 え 四 よん 枚 まい 羽 わ 矢 や 回転 かいてん 三枚 さんまい 羽 わ 矢 や 回転 かいてん 的 てき 対象 たいしょう 物 ぶつ 取 と 殺傷 さっしょう 力 りょく 強化 きょうか [ 2]
現在 げんざい 競技 きょうぎ 用 もち 矢 や 三 さん 枚 まい 羽 わ 羽 はね 名前 なまえ 付 つ
走 はし 羽 はね 矢 や 弦 つる 番 つが 上側 うわがわ 垂直 すいちょく 羽 はね 頬 ほお 摺 すり 羽 わ 矢 や 弦 つる 番 つが 手前 てまえ 下 か 側 がわ 羽 はね 矢 や 引 ひ 頬 ほお 触 ふ 呼 よ 弓 ゆみ 摺 すり 羽 わ 外 そと 掛 かけ 羽 わ 矢 や 弦 つる 番 つが 向 む 側 がわ 下 した 羽 はね 矢 や 末端 まったん 弦 つる 番 つが 部分 ぶぶん 古 ふる 箆 へら 切込 きりこ 入 い 弓 ゆみ 強力 きょうりょく 引 ひ 際 さい 箆 へら 裂 さ 弦 つる 溝 みぞ 頭 あたま 状 じょう 筈 はず 部品 ぶひん 筈 はず 金属 きんぞく 現在 げんざい 角 かく 作 つく 箆 へら 挿 さ 込 こ 後 のち 筈巻 はずまき 糸 いと 巻 ま 固定 こてい
鏃と同 おな 長 なが 使用 しよう 抜 ぬ 落 お 欠 か 時 とき 交換 こうかん
筈 はず 弦 つる 当然 とうぜん 当然 とうぜん 筈 はず 今 いま 筈 はず 筈 はず 回 いまわ 残 のこ
ちなみに、同 おな 書 か 場合 ばあい 弓 ゆみ 上下 じょうげ 弦 つる 掛 か 部分 ぶぶん 指 さ 混同 こんどう 避 さ 筈 はず 矢筈 やはず 弓 ゆみ
アーチェリーでは、矢 や 呼 よ 使用 しよう 者 しゃ 体格 たいかく 及 およ 使用 しよう 弓 ゆみ 引 び 重量 じゅうりょう 応 おう 固 かた 長 なが 重量 じゅうりょう 調整 ちょうせい 作成 さくせい
先端 せんたん 取 と 付 つ 金具 かなぐ 挿 さ 込 こ ホットメルト接着 せっちゃく 剤 ざい を用 もち 固定 こてい 使用 しよう 弓 ゆみ 引 び 重量 じゅうりょう 応 おう 重量 じゅうりょう 調整 ちょうせい ボドキンポイント (英語 えいご 版 ばん
矢 や 胴体 どうたい 部分 ぶぶん 素材 そざい 繊維 せんい 強化 きょうか ジュラルミン などが使 つか 炭素 たんそ 繊維 せんい 強化 きょうか 主流 しゅりゅう 形状 けいじょう 樽 たる 状 じょう ストレートシャフト などがある。アメリカのイーストン社 しゃ が世界 せかい 最大 さいだい 弩 いしゆみ 使 つか 物 もの 比較的 ひかくてき 短 みじか
アローに取 と 付 つ 羽 はね 鳥 とり 羽根 ばね 製 せい 製 せい 製 せい 小 ちい 矢 や 集中 しゅうちゅう 力 りょく 良 よ 被害 ひがい 大 おお 対 たい 大 おお 多少 たしょう 悪 わる 被害 ひがい 最小限 さいしょうげん 一般 いっぱん 的 てき 初心者 しょしんしゃ 大 おお 上級 じょうきゅう 者 しゃ 小 ちい 用 もち 弩 いしゆみ 使 つか 物 もの 枚数 まいすう 減 へ 場合 ばあい 矢 や 羽 わ 自体 じたい
一本 いっぽん 矢 や 対 たい 度 ど 間隔 かんかく 枚 まい 貼 は 一般 いっぱん 的 てき
コックフェザー
ノックの溝 みぞ 弓 ゆみ 対 たい 直角 ちょっかく 羽根 はね 異 こと 色 いろ 使 つか
ヘンフェザー
コックフェザーに対 たい 度 ど 間隔 かんかく 羽根 はね ストリング(弦 つる 部分 ぶぶん 矢筈 やはず プラスチック 製 せい
鋭 するど 器 き 損傷 そんしょう 切 せつな 創 そう 刺 とげ 創 そう (英語 えいご 版 ばん 組 く 合 あ [ 3]
創傷 そうしょう 弾 だん 道学 どうがく (ドイツ語 ご 版 ばん ) 矢 や 傷 きず 実験 じっけん 弾道 だんどう (英語 えいご 版 ばん 石鹸 せっけん 組 く 合 あ 使 つか 実験 じっけん 多 おお 不向 ふむ 意見 いけん [ 3] 豚 ぶた 死骸 しがい 使 つか 実験 じっけん 先 さき 平均 へいきん 射抜 いぬ 際 さい 矢尻 やじり 異 こと 骨 ほね 場所 ばしょ 突 つ 刺 さ 矢尻 やじり 肋骨 あばらぼね 骨 ほね 貫通 かんつう 威力 いりょく 致命傷 ちめいしょう 傷 きず 深 ふか 確認 かくにん [ 3] 西武 せいぶ 時代 じだい 医師 いし 記録 きろく 先住民 せんじゅうみん 矢 や 接近 せっきん 戦 せん 直撃 ちょくげき 頭 あたま 骨 ほね 貫通 かんつう 弓 ゆみ 兵 へい 熟知 じゅくち 致命傷 ちめいしょう 胴体 どうたい 狙 ねら 多 おお 記 しる [ 4]
日本 にっぽん 戦国 せんごく 時代 じだい 金 きむ 創 はじめ 医 い 治療 ちりょう 行 おこな 江戸 えど 時代 じだい 絵師 えし 歌川 うたがわ 国芳 くによし 華 はな 羽 わ 箭 や 療治 りょうじ 図 ず 通俗 つうぞく 三国志 さんごくし 演義 えんぎ 中 ちゅう 述 の 医者 いしゃ 華 はな 関 せき 羽 わ 将軍 しょうぐん 毒矢 どくや 取 と 除 のぞ 手術 しゅじゅつ 行 おこな 様子 ようす 描 えが [ 5] [ 6]
古 ふる 記録 きろく 記述 きじゅつ 書 か 人間 にんげん 古代 こだい 学者 がくしゃ ケルスス がいる。著書 ちょしょ 章 しょう 矢 や 傷 きず 治療 ちりょう 割 さ 中 なか 抜 ぬ 取 と 貫通 かんつう 出 だ 重要 じゅうよう 性 せい Spoon of Diocles (英語 えいご 版 ばん 外科 げか 器具 きぐ 記述 きじゅつ 抜 ぬ 取 と 貫通 かんつう 意図 いと 抜 ぬ 取 と 矢尻 やじり 抜 ぬ 体内 たいない 残 のこ 弊害 へいがい 起 お 矢 や 傷 きず 少 すく 現代 げんだい 起 お 事故 じこ 指摘 してき [ 7]
イギリスでは、矢柄 やがら 外 はず 矢尻 やじり 頬 ほお 刺 さ 世 せい 救 すく 貨幣 かへい 偽造 ぎぞう 罪 つみ 釈放 しゃくほう ジョン・ブラッドモア (英語 えいご 版 ばん 金属 きんぞく 加工 かこう 技術 ぎじゅつ 作 つく 抜 ぬ 道具 どうぐ 治療 ちりょう 技術 ぎじゅつ 宮廷 きゅうてい 外科 げか 医 い [ 8]
アメリカの西部 せいぶ 開拓 かいたく 時代 じだい 先住民 せんじゅうみん 戦 たたか 際 さい 治療 ちりょう 行 おこな 医師 いし 記録 きろく 他 た 武器 ぶき 致命 ちめい 的 てき 傷 きず 負 お 治療 ちりょう 受 う 場合 ばあい 特 とく 記 しる 様々 さまざま 素材 そざい 矢尻 やじり 作 つく 先住民 せんじゅうみん 最 もっと 用 もち 金属 きんぞく 削 けず 矢柄 やがら ミズキ属 ぞく (dogwood)の枝 えだ 連射 れんしゃ 速度 そくど 熟練 じゅくれん 分間 ふんかん 発 はつ 放 はな 人 にん 兵士 へいし 発 はつ 傷 きず 負 お 本 ほん 矢 や 傷 きず 見 み 銃 じゅう 貫通 かんつう 矢尻 やじり 大量 たいりょう 体内 たいない 残 のこ 治療 ちりょう 難 むずか [ 4]
その時代 じだい 治療 ちりょう 法 ほう 矢 や 引 ひ 抜 ぬ 愚策 ぐさく 記 しる 腱 けん 使 つか 矢尻 やじり 固定 こてい 血 ち 体液 たいえき 緩 ゆる 簡単 かんたん 外 はず 抜 ぬ 矢尻 やじり 探 さが 難 むずか 矢柄 やがら 残 のこ 沿 そ 切開 せっかい 取 と 除 の 予 よ 後 ご 自然 しぜん 治 なお 矢尻 やじり 貫通 かんつう 体外 たいがい 出 で 逆 ぎゃく 治療 ちりょう 骨 ほね 貫通 かんつう 治療 ちりょう 難 なん 度 ど 上 あ 矢柄 やがら 回 まわ 動 うご 骨 ほね 貫通 かんつう 判断 はんだん 骨 ほね 貫通 かんつう 場合 ばあい 矢尻 やじり 特別 とくべつ 傷口 きずぐち 侵入 しんにゅう 細 ほそ 鉗子 で掴 つか 渾身 こんしん 力 ちから 使 つか 引 ひ 抜 ぬ 作業 さぎょう 求 もと 骨 ほね 近 ちか 筋肉 きんにく 痛 いた 反応 はんのう 収縮 しゅうしゅく 矢尻 やじり 状 じょう 一度 いちど 矢尻 やじり 押 お 込 こ 方法 ほうほう 有効 ゆうこう 失 しつ 血 ち 神経 しんけい 損傷 そんしょう 合併症 がっぺいしょう 見 み [ 4]
もちろん、矢 や 死者 ししゃ 出 で [ 3] 致命傷 ちめいしょう 矢 や 傷 きず 銃創 じゅうそう 半 はん 矢 や 呼 よ
ミームとして、膝 ひざ 矢 や 受 う 知 し
『古事記 こじき 国 くに 譲 ゆず 神話 しんわ 次 つぎ 始 はじ
高木 たかぎ 神 かみ 天照大御神 あまてらすおおみかみ 中 なか 国 くに 荒 すさ 国 くに 神 しん 服従 ふくじゅう 天 てん 神 しん 命 めい 天 てん 神 しん 復命 ふくめい 次 つぎ 天若 あまわか 日子 にっし 命 めい 天若 あまわか 日子 にっし 中 なか 国 くに 住 す 今度 こんど 鳴 な 女 おんな 様子 ようす 見 み 行 い 天若 あまわか 日子 にっし 天 てん 佐 さ 具 ぐ 売 うり 鳴 な 女 おんな 高 こう 御産 おさん 巣 す 日 び 神 しん 高木 たかぎ 神 かみ 授 さず 矢 や 射殺 しゃさつ 矢 や 鳴 な 女 おんな 体 からだ 突 つ 抜 ぬ 高木 たかぎ 神 かみ 許 もと 届 とど 不審 ふしん 思 おも 高木 たかぎ 神 かみ 天若 あまわか 日子 にっし 悪 あ 神 かみ 討 う 矢 や 天若 あまわか 日子 にっし 邪心 じゃしん 持 も 矢 や 天若 あまわか 日子 にっし 誓約 せいやく 矢 や 投 な 返 がえ 矢 や 天若 あまわか 日子 にっし 当 あ 天若 あまわか 日子 にっし 死 し 返 かえ 矢 や 天 てん 之 の 返 かえ 矢 や
さまざまな古文 こぶん 句 く 使 つか 俳句 はいく 季語 きご 同 おな 間接 かんせつ 的 てき 比喩 ひゆ 穢 けが 邪気 じゃき 魔 ま 厄 やく 祓 はら 清 きよ 表 あらわ 言葉 ことば
葦 あし 矢 や 葦 あし 矢 や 桃 もも 弓 ゆみ 弓 ゆみ 一対 いっつい 葦 あし 矢 や 桃 もも 弓 ゆみ 大晦日 おおみそか 朝廷 ちょうてい 行 おこな 追 つい 式 しき 鬼 おに 祓 はら 為 ため 使 つか 弓矢 ゆみや 葦 あし アシ )の茎 くき 桃 もも 木 き 出来 でき
破魔矢 はまや 破魔矢 はまや 破魔弓 はまゆみ 一対 いっつい 正月 しょうがつ 行 おこな 年 とし 吉凶 きっきょう 占 うらな 使 つか 弓矢 ゆみや 後 のち 家内 かない 安全 あんぜん 祈願 きがん 幣 ぬさ 串 くし 同 おな 家 いえ 鬼 おに 祓 はら 魔除 まよけ 上棟 じょうとう 式 しき 小屋 こや 組 ぐみ 奉納 ほうのう 神祭 しんさい 具 ぐ 近年 きんねん 破魔矢 はまや 破魔弓 はまゆみ 神社 じんじゃ 厄除 やくよ 縁起物 えんぎもの 知 し
蓬 よもぎ 矢 や 蓬 よもぎ 矢 や 桑弓 くわゆみ 一対 いっつい 蓬 よもぎ 矢 や 桑 くわ 弓 ゆみ 男 おとこ 子 こ 生 う 時 とき 前途 ぜんと 厄 やく 払 はら 家 いえ 四方 しほう 向 む 桑 くわ 弓 ゆみ 蓬 よもぎ 矢 や 射 い 桑 くわ 弓 ゆみ 桑 くわ 木 き 作 つく 弓 ゆみ 蓬 よもぎ 矢 や 蓬 よもぎ 葉 は 羽 はね 矧 は 矢 や
儀 ぎ 矢 や 神社 じんじゃ 神事 しんじ 用 よう 神宝 しんぽう 威儀 いぎ 物 ぶつ 神幸 しんこう 等 とう 使 つか 矢 や 儀 ぎ 矢 や 征矢 そや 雁股 かりまた 矢 や 鏑矢 かぶらや 三種 さんしゅ 黒 くろ 漆 うるし 塗 ぬり 矢筈 やはず 水晶 すいしょう 筈巻 はずまき 下作 げさく 共 ども 紅 べに 羽根 はね 白羽根 しらはね 二 に 片 へん 平 ひら 壷 つぼ 盛 も [ 9]
単語 たんご 矢面 やおもて 騒動 そうどう 説明 せつめい 必要 ひつよう 場面 ばめん 最前 さいぜん 当事 とうじ 者 しゃ 立場 たちば 矢 や 返 がえ 報復 ほうふく 仕返 しかえ 意味 いみ 言葉 ことば 矢 や 数 すう 射 い 矢 や 数 かず 的 まと 矢 や 数 かず 通 とお 矢 や 成 な 矢 や 数 かず 矢倉 やくら 矢 や 収蔵 しゅうぞう 倉 くら 武器 ぶき 庫 こ 兵庫 ひょうご 櫓 ろ 意 い 櫓 ろ 意 い 戦 せん 展望 てんぼう 台 だい 矢先 やさき 矢 や 先 さき 矢 や 飛 と 行 い 来 く 場所 ばしょ 矢面 やおもて 同意 どうい 矢 や 開 びら 矢口 やぐち 矢文 やぶみ 矢 や 紋 もん 一 ひと 並 なら 矢 や 矢 や 紋 もん 鏑矢 かぶらや 嚆矢 こうし 鳴 な 矢 や 魔除 まよけ 騎射 きしゃ 三 さん 物 ぶつ 合戦 かっせん 合図 あいず 使用 しよう 鏑 かぶら 唸 うな 矢 や 幸 こう 矢 や 猟 りょう 矢 や 狩 かり 用 もち 矢 や 矢 や 弓矢 ゆみや 運 うん 分 ぶん 天分 てんぶん 幸福 こうふく 幸 みゆき 箭 や 霊 れい 記述 きじゅつ 読 よ 名残 なごり 狩 かり 矢 や 開 びら 使 つか 矢 や 幸 こう 矢 や 猟 りょう 矢 や 記述 きじゅつ 読 よ 征矢 そや 征 せい 箭 や 攻撃 こうげき 力 りょく 高 たか 付 つ 矢 や 遠矢 とおや 遠 とお 矢 や 飛 と 遠方 えんぽう 射 い 火矢 ひや 焙烙 ほうろく 火矢 ひや 毒矢 どくや 慣用 かんよう 句 く 矢継 やつ 早 ばや 矢 や 鉄砲 てっぽう 持 も 来 こ 矢庭 やにわ 矢 や 催促 さいそく 矢 や 楯 だて 矢場 やば やばい )一 いち 箭 や 双 そう 一石二鳥 いっせきにちょう 同義語 どうぎご 一矢 いっし 二 に 羽 わ 鳥 とり 射止 いと 一矢 いっし 報 むく 光陰 こういん 矢 や 白羽 しらは 矢 や 立 た
^ “儀仗 ぎじょう goo辞書 じしょ . 大辞林 だいじりん 年 ねん 月 がつ 10日 とおか 閲覧 えつらん ^ 近藤 こんどう 好和 よしかず 弓矢 ゆみや 刀剣 とうけん 中世 ちゅうせい 合戦 かっせん 実像 じつぞう 第 だい 刷 さつ 吉川弘文館 よしかわこうぶんかん 東京 とうきょう 都 と 文 ぶん 区 く 本郷 ほんごう 歴史 れきし 文化 ぶんか 原著 げんちょ 年 ねん 月 がつ 日 にち 頁 ぺーじ ISBN 4-642-05420-0 。 ^ a b c d Karger, Bernd; Sudhues, Hubert; Kneubuehl, Beat P.; Brinkmann, Bernd (1998-09). “Experimental Arrow Wounds: Ballistics and Traumatology” (英語 えいご The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care 45 (3): 495–501. doi :10.1097/00005373-199809000-00011 . ISSN 1079-6061 . http://journals.lww.com/00005373-199809000-00011 .
^ a b c Harrington, Hugh T. (2013-05-16) (英語 えいご Battle Wounds: Never Pull an Arrow Out of a Body . https://allthingsliberty.com/2013/05/battle-wounds-never-pull-an-arrow-out-of-a-body/ .
^ 石出 いしで 猛 たけし 史 し 年 ねん 月 がつ 華 はな 羽 わ 箭 や 療治 りょうじ 図 ず 千葉 ちば 医学 いがく 雑誌 ざっし 年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ “もうひとつの学芸 がくげい 員 いん 室 しつ 江戸 えど 学 まな 養生 ようじょう 華 はな 羽 わ 箭 や 療治 りょうじ 図 ず ”. エーザイくすりの博物館 はくぶつかん . 2024年 ねん 日 にち 閲覧 えつらん ^ Shereen, Rafik; Oskouian, Rod J; Loukas, Marios; Tubbs, R. Shane (2018-04-13). “Treatment of Arrow Wounds: A Review” (英語 えいご Cureus . doi :10.7759/cureus.2473 . ISSN 2168-8184 . PMC PMC5999391 . PMID 29904614 . https://www.cureus.com/articles/9164-treatment-of-arrow-wounds-a-review . ^ Lang, S. J. (2004). "Bradmore, John (d. 1412), surgeon" Oxford Dictionary of National Biography 英語 えいご doi :10.1093/ref:odnb/45759 . 2023年 ねん 月 がつ 日 にち 閲覧 えつらん 。 (要 よう 購読 こうどく イギリス公立 こうりつ 図書館 としょかん 会員 かいいん 加入 かにゅう 。) ^ 『神社 じんじゃ 有職故実 ゆうそくこじつ 頁 ぺーじ 昭和 しょうわ 年 ねん 月 がつ 日 にち 神社 じんじゃ 本庁 ほんちょう 発行 はっこう
ウィキメディア・コモンズには、
矢 や に
関連 かんれん するカテゴリがあります。
射的 しゃてき 競技 きょうぎ
紋章 もんしょう
漢字 かんじ 部首 ぶしゅ
流派 りゅうは 道着 どうぎ 用具 ようぐ 用語 ようご 主要 しゅよう 大会 たいかい 関連 かんれん 項目 こうもく