ストア派
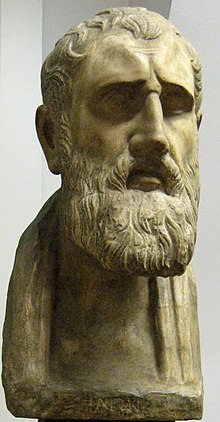
ストア
概要 [編集 ]
ストア
ルキウス・アンナエウス・セネカやエピクテトスのような
ヘレニズム
ストア
基本 的 教 説 [編集 ]
| 「 | 「 |
」 |
—エピクテトス[8] | ||
ストア
ストア
ストア
ストア
ストア
ヘレニズム
歴史 [編集 ]
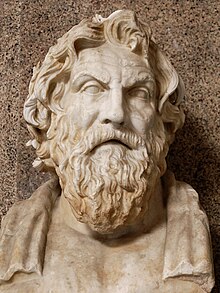
ゼノンの
前期 ストア派 、ゼノンによる学派 の創設 からアンティパトロスまで。中期 ストア派 パナイティオスやポセイドニオスを含 む。後期 ストア派 、ムソニウス・ルフス、ルキウス・アンナエウス・セネカ、エピクテトス、そしてマルクス・アウレリウス・アントニヌスらを含 む。
アルバート・アーサー・ロングが
ストア論 理学 [編集 ]
命題 論理 [編集 ]
ゼノンの
「クリュシッポスは
ストア範疇 論 [編集 ]
基体 (ギリシア語 : ὑποκείμενον)物 がそれから構成 されるところの基本 的 な物質 、形相 を持 たない実体 (ousia)性質 づけられた(もの) (ギリシア語 : ποιόν)物質 が個々 の物体 を形成 する方法 ; ストア自然 学 では、物質 に形相 をもたらす物質 的 な構成 要素 (pneuma:気息 )何 らかの様態 にある(もの)(ギリシア語 : πως ἔχ ο ν )大 きさ、形状 、行動 、体勢 といった特定 の特徴 であり、物体 の内部 に存 するものではない何 かとの関係 において何 らかの様態 にあるもの(ギリシア語 : πρός τί πως ἔχ ο ν )時間 ・空間 内 における他 の物体 との相対 的 位置 のような、他 の現象 との相対 的 な特徴
認識 論 [編集 ]
ストア
あるものがその
実態 において、その裸 の状態 において、その完全 な全体 性 においてどんな種類 のものかを見極 めるために、そしてその適切 な名前 や解決 へ向 けて混合 されたものの名前 を分 かるために、あなたに表象 されたものの定義 ・記述 を自分 のためになしなさい。なぜなら、あなたの生涯 において表象 された物体 を真 に系統的 に観察 し、同時 にこの世界 がどんな世界 であるか、世界 の中 で万物 がどのように働 くか、全体 との関連 の中 で個々 のものがどんな意味 を持 つかを見極 めるために物事 を常 に観察 することほど、心 を練磨 する上 で生産 的 なことはないのだから。—マルクス・アウレリウス・アントニヌス,『
自省 録 』、第 III巻 第 11章
ストア派 の自然 学 ・宇宙 論 [編集 ]
ストア
世界 それ自体 が神 であり、世界 が自身 の霊魂 を流出 する; それは同 じ世界 を導 く原理 であり、物 の一般 的 本性 やあらゆる物質 を包含 する全体 性 とともに心 や理性 の中 で働 く;運命 づけられた力 と未来 の必然 性 ; それにエーテルの炎 と原理 ; さらに水 、大地 、空気 のような本来 の状態 が流動的 ・遷移 的 な諸 元素 ; それから太陽 、月 、星 々; これらと、全 てのものが内包 されるような普遍 的 存在 が含 まれる—クリュシッポス,キケロ『
神 々の本性 について』第 I巻 より
世界 を一 つの実体 と一 つの魂 を備 えた一 つの生命 だと常 に見 なせ; そして万物 が知覚 と、つまりこの一 つの生命 についての知覚 をどうやって持 つのかを観察 せよ; さらに万物 がどのように一 つの運動 と共同 して動 くかを観察 せよ; それから万物 がどのように互 いの原因 となっているかを見 て取 れ;網 の構造 や紡 がれ続 ける糸 をも観察 せよ—マルクス・アウレリウス,『
自省 録 』、第 IV巻 第 40節
ストア
ストア派 は宇宙 のロゴスやヘゲモンコン(理性 や指導原理 )と同一 の神 を信 じ、伝統 的 な神 々を格下 げた。しかしストア派 はこの一 つの神 への崇拝 を行 わなかった。中 ・後期 プラトン主義 者 の哲学 的 言説 の中 で最高 の神 について、一般 的 には神 々ではなく、この一 つの神 が宇宙 の創造 と摂理 に責任 を持 つと語 っている[7]。
アスカロンのアンティオコスはアカデメイア、ペリパトス
ストア派 の神学 [編集 ]
ストア
ストア
ストア派 の倫理 学 ・道徳 論 [編集 ]
ストア
その
ストア
であるが、これはプラトンの
ソクラテスに
善悪 「無 関心 」の理論 [編集 ]
ここでいう「
「アディアポラ」の
アディアポラの
運命 の肯定 と自由 意志 の肯定 [編集 ]
これにより
魂 の鍛練 [編集 ]

ストア
早朝 に自分 に向 って言 う:私 は今日 恩知 らずで、凶暴 で、危険 で、妬 み深 く、無慈悲 な人々 と会 うことになっている。こういった品性 は皆 彼 らが真 の善悪 に無知 であることから生 じるのだ[...]何者 も私 を禍 に巻 き込 むことはないから彼 らのうちの誰 かが私 を傷 つけることはないし、私 が親類 縁者 に腹 を立 てたり嫌 ったりすることもない; というのは私 たちは協 働 するために生 まれてきたからである[...]
アウレリウスに
Seamus Mac Suibhneによって、
感情 からの解放 (理性 主義 )[編集 ]
あらゆる
社会 哲学 [編集 ]
ストア
ストア主義 とキリスト教 [編集 ]
ミラノのアンブロジウスの
クレントスはゼノンの「創造 の火 」にもっと明確 な意味 を与 えたいと思 い、それを表現 するためにプネウマ(「精神 」)という言葉 を最初 に思 いついたのである。この知的 な「精神 」は、火 と同様 に、空気 の流 れや息 に似 た弱 い物質 であるが、本質 的 には温 かみのある性質 を持 っていると考 えられていた。それは神 としての宇宙 に、そして魂 と生命 を与 える原理 としての人間 に内在 していた。ここから、キリスト教 神学 の「聖霊 」、つまり「命 の主 であり与 え主 」に至 るまでは、明 らかに長 い道 のりではない。聖霊 はペンテコステのときに火 の舌 として目 に見 える形 で現 れ、それ以来 、キリスト教 でもストア派 でも、生命 の火 や恩恵 的 な暖 かさという考 えと結 びついてきた[44]。
ストア
マルクス・アウレリウスの『
ユストゥス・リプシウスは、
自殺 をめぐる解釈 の違 い[編集 ]
近代 の用法 [編集 ]
「ストイック」という
ストア派 の引用 [編集 ]
ストア
- 「
自由 は人 の欲求 を満 たすことではなく、欲求 を除去 することで得 られる。」 — (iv.1.175)
- 「
神 はどこにいるのか? あなたの心 の中 に。悪 はどこにあるのか? あなたの心 の中 に。どちらもないのはどこか?心 から独立 なものの所 である。」 — (ii.16.1)
- 「
人間 は物 にかき乱 されるのではなく物 に対 する自分 の考 えにかき乱 されるのだ。」 — (Ench. 5)
- 「それゆえ、もし
不幸 な人 がいたら彼 に自分 が自分 自身 の理由 で不幸 なのだと思 い出 させよう — (iii.24.2)
- 「
私 は私 の長所 に関 して自然 によって形成 された:私 は欠点 に関 して形成 されたわけではない。」 — (iii.24.83)
- 「
自分 自身 以外 の何 物 にも執着 してはならない;自分 から引 き離 された後 に苦痛 しか残 さないようなあなたにならないものに執着 してはならない。」 — (iv.1.112)
- 「
判断 することをやめよ、『私 は傷 ついた』と考 えるのをやめよ、あなたは傷 自体 を免 れているのだ。」 — (viii.40)
- 「
世界 よ、あなたにとって正 しいものはすべて私 にとっても正 しい。あなたにとって時宜 に適 っているものの内 で私 にとって早 すぎたり遅 すぎたりするものなどない。自然 よ、あなたの季 節 がもたらすものは皆 私 にとって実 りある。あなたから全 てのものが生 まれる、あなたの内 に全 てのものがある、あなたに向 かって全 てのものが還 帰 する。」 — (iv.23)
- 「あなたがあなたの
前面 で働 いているなら、あなたが即座 にそれを取 り戻 すことになっているかのように、正 しい理性 があなたを破壊 するようなものはなくあなたの心的 な部分 は純粋 に保 ち、真面目 に、活発 に、静謐 に引 き続 く; もしあなたがそれを保 ち、何 も期待 せず、しかし自然 に従 った今 の生活 に満足 し、あなたが口 にする全 ての言葉 において英雄 的 真理 を述 べるなら、あなたは幸福 に暮 らせるだろう。そして何者 之 を妨害 できない。」 — (iii.12)
- 「
人生 で起 こること全 てにいちいち驚 くのはなんと馬鹿 げていてなんと奇妙 なことだろう!」 — (xii.13)
- 「
外的 なものが魂 に触 れることはない、たとえ最 も僅少 な程度 においても;魂 に入 る許可 が与 えられることもないし、魂 を変化 させたり動 かしたりすることもない; しかし魂 は自身 を変化 ・移動 させられるのだ。」 — (v 19)
- 「あなた
自身 の強 さは役目 と同 じではないのだから、人 の力 を超 えていると思 わないことだ; しかし全 てが人 の権能 ・職分 であるなら、それがあなた自身 の範囲 にも含 まれることを信 じなさい。」 — (vi.19)
- 「あるいはあなたを
悩 ませるものはあなたの名声 なのか? しかし私 たちがどれだけ早 くものを忘 れるかをみよ。間断 なき奈落 が記憶 を全 てのみこんでしまう。その間隙 に拍手 が送 られる。」 — (iv.3)
- 「
問題 は、どれだけ長 く生 きるかではなくどれだけ立派 に生 きるかである。」 — (Ep. 101.15)
- 「
幸福 が私 たちにもたらさないものを彼女 が私 たちから取 り去 ることはできない。」 — (Ep. 59.18)
- 「
自然 に、彼女 が望 むままに彼女 自身 の問題 を取 り扱 わせてみよう;何 があっても勇敢 ・快活 でいよう。滅 びゆくもののうち何 ものも私 たち自身 のものではないことをよく考 えておこう。」 — (De Provid. v.8)
- 「
徳 とは正 しき理性 に他 ならない。」 — (Ep. 66.32)
ストア派 哲学 者 [編集 ]
前期 [編集 ]
- キティオンのゼノン (
紀元前 332年 –紀元前 262年 )、ストア派 及 びアテナイのストア・ポイキレの創設 者 - キオスのアリストン、ゼノンの
弟子 - カルタゴのヘリッロス
- アッソスのクレアンテス (
紀元前 330年 –紀元前 232年 )ストア・ポイキレの第 二 代 学頭 - ソロイのクリュシッポス (
紀元前 280年 –紀元前 204年 )ストア・ポイキレの第 三 代 学頭 - バビロンのディオゲネス (
紀元前 230年 –紀元前 150年 ) - タルソスのアンティパトロス (
紀元前 210年 –紀元前 129年 )
中期 [編集 ]
- ロドスのパナイティオス (
紀元前 185年 –紀元前 109年 ) - アパメアのポセイドニオス (
紀元前 135年 頃 –紀元前 51年 ) - ストア
派 のディオドロス (紀元前 120年 頃 –紀元前 59年 )、キケロの師
後期 [編集 ]
- マルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシス (
紀元前 94年 –紀元前 46年 ) - ルキウス・アンナエウス・セネカ (
紀元前 4年 – 65年 ) - ガイウス・ムソニウス・ルフス
- ルベッリウス・プラウトゥス
- プブリウス・クロディウス・トラセア・パエトゥス
- エピクテトス (55
年 –135年 ) - ヒエロクレス (2
世紀 ) - マルクス・アウレリウス・アントニヌス (121
年 –180年 )
主 な著作 [編集 ]
- クリュシッポス『
論理 学 研究 』(散逸 ) - セネカ
- 『
怒 りについて』(De Ira) - 『
寛容 について』(De Clementia) - 『
賢者 の不動 心 について』(De Constantia Sapientiis) - 『
心 の平静 について』(De Tranquillitate Animi) - 『
人生 の短 さについて』(De Brevitate Vitae) - 『
幸福 な人生 について』(De Vita Beata) - 『
神慮 について』(De Providentia) - 『
善行 について』(De Beneficiis)
- 『
- マルクス・アウレリウス・アントニヌス『
自省 録 』
注釈 [編集 ]
- ^
ο θεός
出典 [編集 ]
- ^ NHK2019
年 4月 1日 放送 、100分 de名著 「マルクス・アウレリウス」『自省 録 』第 1回 自分 の「内 」を見 よ。岸見 一郎 - ^ a b Stoicism, Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- ^ John Sellars. Stoicism, p. 32.
- ^ a b Agathias. Histories, 2.31.
- ^ a b David, Sedley (1998). "Ancient philosophy". In E. Craig (ed.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. 2008
年 10月 18日 閲覧 。 - ^ a b Gnuse, Robert Karl (1 May 1997). No Other Gods: Emergent Monotheism in Israel. Sheffield Academic Press. p. 225. ISBN 1-85075-657-0
- ^ a b c d Brenk, Frederick (January 2016). “Pagan Monotheism and Pagan Cult”. "Theism" and Related Categories in the Study of Ancient Religions. SCS/AIA Annual Meeting. 75.4. Philadelphia: Society for Classical Studies (University of Pennsylvania). オリジナルの6 May 2017
時点 におけるアーカイブ。 2021年 8月 3日 閲覧 . "Historical authors generally refer to “the divine” (to theion) or “the supernatural” (to daimonion) rather than simply “God.” [...] The Stoics, believed in a God identifiable with the logos or hegemonikon (reason or leading principle) of the universe and downgraded the traditional gods, who even disappear during the conflagration (ekpyrosis). Yet, the Stoics apparently did not practice a cult to this God. Middle and Later Platonists, who spoke of a supreme God, in philosophical discourse, generally speak of this God, not the gods, as responsible for the creation and providence of the universe. They, too, however, do not seem to have directly practiced a religious cult to their God." - ^ Epictetus, Discourses 1.15.2, Robin Hard revised translation.
- ^ a b Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 254.
- ^ a b Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 264.
- ^ Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy, p. 253.
- ^ Charles Hartshorne and William Reese, "Philosophers Speak of God," Humanity Books, 1953 ch 4
- ^ Amos, H. (1982). These Were the Greeks. Chester Springs: Dufour Editions. ISBN 978-0-8023-1275-4. OCLC 9048254
- ^ Gilbert Murray, The Stoic Philosophy (1915), p.25. In Bertrand Russell, A History of Western Philosophy (1946).
- ^ Becker, Lawrence (2003). A History of Western Ethics. New York: Routledge. p. 27. ISBN 978-0-415-96825-6
- ^ A.A.Long, Hellenistic Philosophy, p.115.
- ^ [1] Stanford Encyclopedia of Philosophy: Susanne Bobzien, Ancient Logic
- ^ [2] Stanford Encyclopedia of Philosophy: Susanne Bobzien, Ancient Logic
- ^ Diogenes Laërtius (2000). Lives of eminent philosophers. Cambridge, MA: Harvard University Press VII.49
- ^ Seneca, Epistles, lxv. 2.
- ^ Marcus Aurelius, Meditations, iv. 21.
- ^ Zeller 1931, p. 274.
- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 8. "One way of justifying to themselves and to others their attachment to specific gods was to proclaim that what was really being worshipped under various names and historically sanctioned forms of cult was the one ineffable principle of all things. Unambiguously professed in a sentence like the following: ‘God being one, has many names’,12 this belief permeates Greek religious theory. The Stoic Cleanthes can thus address a fervent hymn to Zeus as a god with a definite historical personality, in which we encounter a monistic view of divinity.13 Indeed this may be the reason why this pagan prayer was selected by Stobaeus, along with a similar Orphic hymn to Zeus, for the anthology that he compiled for his son’s use and education"
- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 19. "Platonists and Aristotelians defined God as absolutely immaterial and therefore transcending the world of the senses, while the Stoics taught that, though incorporeal, God displays a form of materiality, but of a very subtle and literally ethereal nature, and likened him to intelligible light or fire. Yet, as is argued in the second chapter of this volume, both had a monotheistic view, and the Christians, who drew on Greek philosophy for the formulation of their own theology, recognized this. Of the two views on offer orthodox Christianity opted for the first, without however being able to reject the Stoic position altogether, as Tertullian’s rhetorical question testifies: ‘for who will deny that God is a body, though he is a spirit?’48 This ambiguity is even more clearly present in pagan theological literature, which combines belief in a transcendental God with the worship of the Sun seen as the representation of God in this world."
- ^ a b Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), pp. 43-44. "the Platonists, the Peripatetics, and the Stoics do not just believe in one highest god, they believe in something which they must take to be unique even as a god. For they call it ‘God’ or even ‘the God’, as if in some crucial way it was the only thing which deserved to be called ‘god’. If, thus, they also believe that there are further beings which can be called ‘divine’ or ‘god’, they must have thought that these further beings could be called ‘divine’ only in some less strict, diminished, or derived sense. Second, the Christians themselves speak not only of the one true God, but also of a plurality of beings which can be called ‘divine’ or ‘god’; for instance, the un-fallen angels or redeemed and saved human beings."
- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 53. "Nevertheless, this clearly means that only Zeus satisfies the criterion for being a god fully, whereas all other gods only satisfy the criterion by not insisting on strict indestructibility, but by accepting a weak form of immortality. It is only in this diminished sense that things other than Zeus can be called ‘god’. More importantly, though, these other gods only exist because the God has created them as part of his creation of the best possible world, in which they are meant to play a certain role. The power they thus have is merely the power to do what the God has fated them to do. They act completely in accordance with the divine plan......It is very clear in their case, even more so than in Aristotle’s, that these further divine beings are radically dependent on the God and only exist because they have a place in the divine order of things. Far from governing the universe or having any independent share in its governance, they only share in the execution of the divine plan; they are not even immortal, strictly speaking. Theirs is a rather tenuous divinity."
- ^ Pagan Monotheism in Late Antiquity, Edited by Polymnia Athanassiadi, Michael Frede, CLARENDON PRESS • OXFORD(1999), p. 51. "But the Stoics not only think that all beings are material or corporeal, they also, more specifically, identify God or Zeus with a certain kind of fire which is supposed to be intelligent, active, and creative. So perhaps we have to assume that the Stoics distinguish two aspects of the fiery substance which is Zeus, two aspects, though, which in reality are never separated, namely its divine, creative character, and its material character. Thus God and Zeus are the same to the extent that Zeus is active, creative, intelligent. Now the Stoics also believe that the world is a rational animal that periodically turns entirely into the fiery substance which is Zeus. What happens is that the reason of this animal is itself constituted by this fiery substance, and that this reason slowly consumes and absorbs into itself the soul and the body of the world. Thus, in this state of conflagration, the world, the reason of the world, and Zeus completely coincide."
- ^ “Passion”. Merriam-Webster. Encyclopædia Britannica. 2011
年 1月 29日 閲覧 。 - ^ Graver, Margaret (2009). Stoicism and Emotion. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-30558-5. OCLC 430497127
- ^ Seddon, Keith (2005). Epictetus' Handbook and the Tablet of Cebes. New York: Routledge. p. 217. ISBN 978-0-415-32451-9. OCLC 469313282
- ^ a b Don E. Marietta, (1998), Introduction to ancient philosophy, pages 153-4. Sharpe
- ^ Cato's suicide in Plutarch AV Zadorojnyi, The Classical Quarterly, 2007
年 - ^ William Braxton Irvine, (2009), A guide to the good life: the ancient art of Stoic joy, Oxford University Press, p. 200.
- ^ Davidson, A.I. (1995) Pierre Hadot and the Spiritual Phenomenon of Ancient Philosophy, in Philosophy as a Way of Life, Hadot, P. Oxford Blackwells pp. 9-10.
- ^ Hadot, P. (1992) La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle. Paris, Fayard, pp. 106-115.
- ^ Hadot, P (1987) Exercices spirituels et philosophie antique. Paris, 2nd edn, p. 135.
- ^ Mac Suibhne, S. (2009). “'Wrestle to be the man philosophy wished to make you': Marcus Aurelius, reflective practitioner”. Reflective Practice 10 (4): 429–436. doi:10.1080/14623940903138266.
- ^ Robertson, D (2010). The Philosophy of Cognitive-Behavioral Therapy: Stoicism as Rational and Cognitive Psychotherapy. London: Karnac. ISBN 978-1-85575-756-1
- ^ Epictetus, Discourses, ii. 5. 26
- ^ Epictetus, Discourses, i. 9. 1
- ^ Seneca, Moral letters to Lucilius, Letter 47: On master and slave, 10, circa 65 AD.
- ^ “On the Duties of the Clergy”. www.newadvent.org. 2017
年 3月 1日 閲覧 。 - ^ Aurelius, Marcus (1964). Meditations. London: Penguin Books. p. 26. ISBN 978-0-140-44140-6
- ^ a b Marcus Aurelius (1964). Meditations. London: Penguin Books. p. 25. ISBN 978-0-140-44140-6
- ^ a b c Ferguson, Everett. Backgrounds of Early Christianity. 2003, page 368.
- ^ Grafton, Anthony; Most, Glenn W.; Settis, Salvatore (2010-10-25) (
英語 ). The Classical Tradition. Harvard University Press. p. 911. ISBN 978-0-674-03572-0 - ^
森本 あんり『現代 に語 りかけるキリスト教 』日本 キリスト教団 出版 局 、1998年 、79頁 。ISBN 9784818403307。 - ^
森本 あんり『現代 に語 りかけるキリスト教 』日本 キリスト教団 出版 局 、1998年 、81頁 。ISBN 9784818403307。 - ^ Harper, Douglas (2001
年 11月). “Online Etymology Dictionary — Stoic”. 2006年 9月 2日 閲覧 。 - ^ Baltzly, Dirk (2004
年 12月13日 ). “Stanford Encyclopedia of Philosophy — Stoicism”. 2006年 9月 2日 閲覧 。
参考 文献 [編集 ]
一般 書 [編集 ]
一 次 文献 [編集 ]
- A. A. Long and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Inwood, Brad & Gerson LLoyd P. (eds.) The Stoics Reader: Selected Writings and Testimonia Indianapolis: Hackett 2008.
- Long, George Enchiridion by Epictetus, Prometheus Books, Reprint Edition, January 1955.
- Gill C. Epictetus, The Discourses, Everyman 1995.
- Hadas, Moses (ed.), Essential Works of Stoicism (1961: Bantam)
- Harvard University Press Epictetus Discourses Books 1 and 2, Loeb Classical Library Nr. 131, June 1925.
- Harvard University Press Epictetus Discourses Books 3 and 4, Loeb Classical Library Nr. 218, June 1928.
- Long, George, Discourses of Epictetus, Kessinger Publishing, January 2004.
- Lucius Annaeus Seneca the Younger (transl. Robin Campbell), Letters from a Stoic: Epistulae Morales Ad Lucilium (1969, reprint 2004) ISBN 0-14-044210-3
- Marcus Aurelius Antoninus, Meditations, translated by Maxwell Staniforth; ISBN 0-14-044140-9, or translated by Gregory Hays; ISBN 0-679-64260-9.
- Oates, Whitney Jennings, The Stoic and Epicurean philosophers, The Complete Extant Writings of Epicurus, Epictetus, Lucretius and Marcus Aurelius, Random House, 9th printing 1940.
研究 書 [編集 ]
- Bakalis, Nikolaos, Handbook of Greek Philosophy: From Thales to the Stoics. Analysis and Fragments, Trafford Publishing, May 2005, ISBN 1-4120-4843-5
- Becker, Lawrence C., A New Stoicism (Princeton: Princeton Univ. Press, 1998) ISBN 0-691-01660-7
- Brennan, Tad, The Stoic Life (Oxford: Oxford University Press, 2005; paperback 2006)
- Brooke, Christopher. Philosophic Pride: Stoicism and Political Thought from Lipsius to Rousseau (Princeton UP, 2012) excerpts
- Inwood, Brad (ed.), The Cambridge Companion to The Stoics (Cambridge: Cambridge University Press, 2003)
- Irvine, William, A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy (Oxford: Oxford University Press, 2008) ISBN 978-0-19-537461-2
- Long, A. A., Stoic Studies (Cambridge University Press, 1996; repr. University of California Press, 2001) ISBN 0-520-22974-6
- Robertson, Donald, The Philosophy of Cognitive-Behavioral Therapy: Stoicism as Rational and Cognitive Psychotherapy (London: Karnac, 2010) ISBN 978-1-85575-756-1
- Sellars, John, Stoicism (Berkeley: University of California Press, 2006) ISBN 1-84465-053-7
- Stephens. William O., Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom (London: Continuum, 2007) ISBN 0-8264-9608-3
- Strange, Steven (ed.), Stoicism: Traditions and Transformations (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004) ISBN 0-521-82709-4
- Zeller, Eduard; Reichel, Oswald J., The Stoics, Epicureans and Sceptics, Longmans, Green, and Co., 1892
- Zeller, Eduard (1931), Outlines of the History of Greek Philosophy (13th ed.).
関連 項目 [編集 ]
外部 リンク[編集 ]
- Stoicism (
英語 ) - スタンフォード哲学 百科 事典 「Dirk Baltzly」の項目 。 - Stoicism (
英語 ) - インターネット哲学 百科 事典 「ストア派 」の項目 。 - Stoic Philosophy of Mind (
英語 ) -同 「ストア派 」の項目 。 - The Stoic Library
- The Rebirth of Stoicism
- Stoic Logic: The Dialectic from Zeno to Chrysippus
- Annotated Bibliography on Ancient Stoic Dialectic
- BBC Radio 4's In Our Time programme on Stoicism (requires RealAudio)
- An introduction to Stoic Philosophy
- Online Stoic Community: New Stoa
